許されざる者
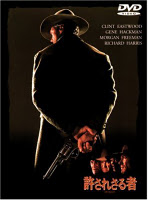 クリント・イーストウッド監督が「最後の西部劇」として撮った、渾身の一作と言われる「許されざる者」。19世紀末のワイオミングを舞台にした、この作品の映像は、たしかに美しく、荒野に広がる光は伸びやかで、世界は印象派の水彩画のようだ。しかし、登場人物がみな、どこかうつろで陰鬱な雰囲気をたたえたこの映画は、単純な西部劇ではない。「殺し合い」が見せ場のはずの西部劇で「殺し」が哲学的問題となっていて、見る者に考えることを強要する。しかし、だからといって、この映画が面白くないわけではない。少なくともエンド・クレジットの10分前までは。
クリント・イーストウッド監督が「最後の西部劇」として撮った、渾身の一作と言われる「許されざる者」。19世紀末のワイオミングを舞台にした、この作品の映像は、たしかに美しく、荒野に広がる光は伸びやかで、世界は印象派の水彩画のようだ。しかし、登場人物がみな、どこかうつろで陰鬱な雰囲気をたたえたこの映画は、単純な西部劇ではない。「殺し合い」が見せ場のはずの西部劇で「殺し」が哲学的問題となっていて、見る者に考えることを強要する。しかし、だからといって、この映画が面白くないわけではない。少なくともエンド・クレジットの10分前までは。
「許されざる者」( UNFORGIVEN )というタイトルが示すように、この映画のテーマは「憤怒による復習、そして当然の報いとしての死」だ。理由は何であれ、他人を傷つけたり殺したりしてしまった者は、決して「許されることは無い」というのが、この映画の世界における究極のルールだ。このメッセージは明快だ。この映画でも、悪いことをした連中は、ちゃんとストーリーの中で、みなしっかりと罰を受けることになる。
リチャード・ハリス演じる、イギリス人賞金稼ぎのイングリッシュ・ボブ(リチャード・ハリスの存在感は圧倒的)は、とりあえずの罪としては、イギリス女王とアメリカ大統領を比較して大統領をコケにするだけというものだが、おそらくはこれまで散々と殺人を犯したであろうことから、登場からたった数分後には滅茶苦茶な目に遭わされることになる。
そのイングリッシュ・ボブを片付けた、破天荒な保安官、リトル・ビル・ダゲット(ジーン・ハックマン)は、結構まっとうな正義漢でもあり、その手腕はなかなかのもの(リオ・ブラボーでの、ジョン・ウェインよりましでないか)なのだ。
とはいえ、彼の過剰な暴力には目に余るものがある。このキャラは、いずれ「自業自得」ということで片付けられるのが運命だ。マーニー(イーストウッド)の親友、ネッド・ローガン(モーガン・フリーマン)を拷問で殺害した罪は許されるはずがない。マーニーによって派手に殺されてしまう。ダゲットは最後に「地獄で待ってるぜ」と言い残すのだが、いくら地獄で待ってても、勝ち目が無いのは明らかだ。悪者だもん。
そもそもの、この映画の大騒動のきっかけとなった娼婦傷害事件を引き起こした、牧童のクィック・マイクは、トイレにしゃがんでいるところをズドンズドンと撃ち抜かれて死ぬ。すべてが因果応報なのだ。マイクと一緒に娼婦館にいたために巻き込まれた、牧童デイビィはちょっととばっちりだけど、やっぱしこれも、自業自得ということで片付けられてしまう。この罪の小さなデイビィを、崖から狙撃するマーニーは、冷徹そのもので、彼の過去における極悪非道の数々を想起させる。
いろいろなところで、いろいろな悪いヤツが「因果応報」の原理に片付けられていく内に、観客はだんだん不安になってくる。なぜならば、昔の非道の数々を反省して、今は亡き良妻によって完全に更正したはずの主人公マーニーが、どんどん「悪人」に戻っていってしまうのだ。はじめは、子どもたちとの貧乏な暮らしを抜け出すための「出稼ぎ」という、ちょっとした仕事にすぎなかったはずだ。しかしいつのまにか、傷つけられた娼婦ための「敵討ち殺人」に発展し、ついには親友ネッドの「弔い合戦」の大量殺戮にまで、その行為はエスカレートしていく。ダゲットや街の自警団をひとまとめに片付けるところなど、これはまるで、小林正樹監督の「切腹」を彷彿とさせるような緊迫のバイオレンス。(撃ち合いの時間はあっという間だけど)
しかも、前述のようにダゲットをやっつけるときのやりかたは残虐そのもの。もうこのへんから観客は覚悟を決めるだろう。「ついに、われらがウィリアム・マーニーは、ただの悪党に戻っちまったぞ。ラストシーンはもう、ろくなことにはならない。良妻による献身的な愛によって、真人間になったはずの主人公も、過去の因業を背負って死んでいくのだな〜」と考えて当然だ。これが、ジョージ・ロイ・ヒル監督作品であれば、ラストシーンは、主人公が蜂の巣にされちゃう、感傷的なスローモーションと決まったようなものだ。
しかし、この映画はクリント・イーストウッド監督による、ハリウッドのメジャー作品なのだ。そんなエンディングをくっつけて、観客から生きる希望を奪ってどうするのだ。これが監督の判断かプロデューサーの判断かは知らないが、この最後の10分間は、世界のルールが全面的に変更となる。「因果応報」の原理によって罰を受けるのは、助演男優賞をとったジーン・ハックマンなど、脇役だけに限られる。主人公のウィリアム・マーニーは「反省をした功績、亡き良妻に対する貞操、親友の敵を倒すという仁義」といった美徳によって、過去における大量殺人の罪は、特赦による減免となるのだ。エンドクレジットで「彼と彼の家族が西部において商売に成功したらしい」というグッドニュースまで伝えられ、観客は胸をなで下ろして、幸せな結論に満足する。
アメリカ的な楽観主義というか飛躍的倫理観というご都合主義、つまりこれこそが、ハリウッドにおけるエンタテインメント映画制作の鉄則なのだ。映画が難しい理屈をこねて、理不尽な結末にたどりついて、観客をがっかりさせてどうするんじゃい。せっかく最後まで椅子に座っていてくれた、お客様への思いやりの鉄則。最後は、感情移入をした主人公とともに幸せにひたらなくちゃね。
 佐々木和郎 BLOG
佐々木和郎 BLOG MOVIE
MOVIE